医薬品の品質を守る、縁の下の力持ち――防虫・防鼠対策とGDP
医薬品は人の健康に関わる重要な製品です。その品質を確実に保つために設けられているルールが、「GDP(Good Distribution Practice)」、すなわち「医薬品の適正流通基準」です。
この基準には、温度や湿度、セキュリティといった要素だけでなく、「防虫・防鼠」といった、一見地味ながらも極めて重要な要素が含まれています。

医薬品輸送および倉庫内においては特に施設は清潔で乾燥し、許容可能な温度範囲に維持する事になっています。
今回は防虫防鼠対策について考えて行きたいと思います。
医薬品は人の健康に関わる重要な製品です。その品質を確実に保つために設けられているルールが、「GDP(Good Distribution Practice)」、すなわち「医薬品の適正流通基準」です。
この基準には、温度や湿度、セキュリティといった要素だけでなく、「防虫・防鼠」といった、一見地味ながらも極めて重要な要素が含まれています。
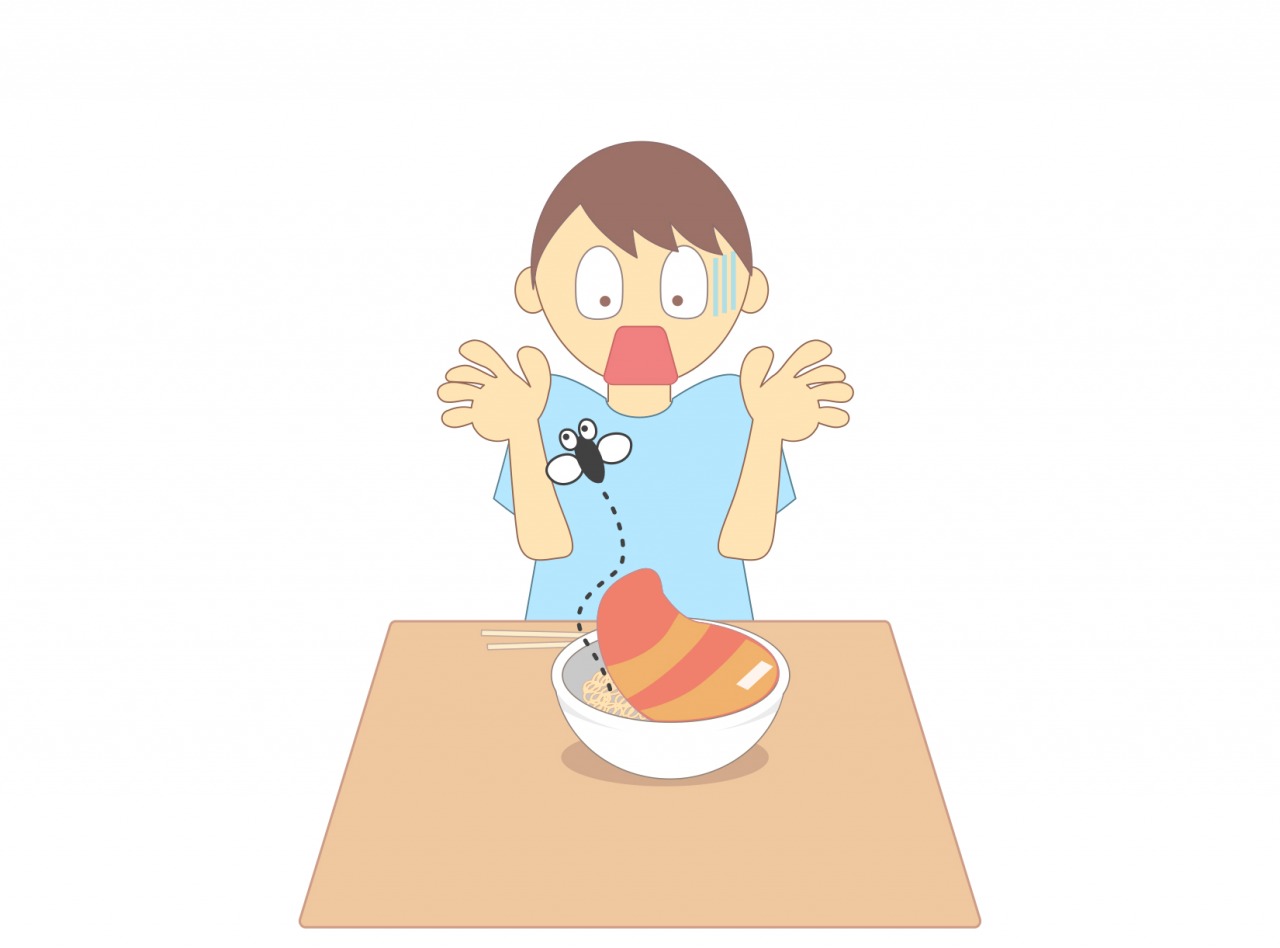
倉庫に入り込んだネズミや虫が、医薬品に直接触れることは稀かもしれません。
しかし、フンや死骸、体液などが製品に付着すれば、それだけで「異物混入」となり、回収や廃棄の対象になります。製品のパッケージをかじられたり、段ボールの中に巣を作られたりする被害も見逃せません。
このような問題は、医薬品の「信頼」を根本から揺るがすものです。特に最近では、サプライチェーン全体におけるリスク管理が重視されており、わずかな管理の緩みが、大きな損失や信頼の失墜に繋がります。
GDPガイドライン(厚生労働省「医薬品の適正流通基準ガイドライン」)では、医薬品を保管する施設が「清潔で、製品が汚染されることがないよう維持されていること」が求められています。
また、「害虫・害獣の侵入を防ぐための対策を講じていること」も明記されています。
この「清潔であること」「害虫・害獣の侵入防止」が、まさに防虫防鼠対策の根幹です。
では、現場でどのような防虫・防鼠対策が求められているのでしょうか? いくつかのポイントを見てみましょう。
建物の構造的対策:ドアやシャッターに隙間がないか、排水口や換気口に網が設置されているかなど、物理的な侵入経路の封鎖。
清掃と衛生管理:倉庫内外に食べ物のゴミや水たまりがないようにし、ネズミや虫を「呼び寄せない」環境を保つ。
モニタリングと記録:粘着トラップの設置や定期点検によって、侵入の有無を可視化し、記録に残す。
専門業者との連携:定期的に専門業者による点検や駆除を行い、リスクの早期発見と対処に努める。
防虫防鼠対策は、決して華やかな仕事ではありません。しかし、その積み重ねこそが、医薬品の品質と企業の信頼を支えています。
「今日も虫が1匹もいなかった」――それは、誰かの健康を守るための、大切な成果なのです。
作成 :薬剤師 菅沼一茂
次世代の物流環境に対応した体制構築をサポートいたします。
安心・安全な物流パートナーをお探しなら、ぜひ一度お問い合わせください。
メディカル担当
電話:0548-32-0770
e-mail:sales@marusoh-el.co.jp